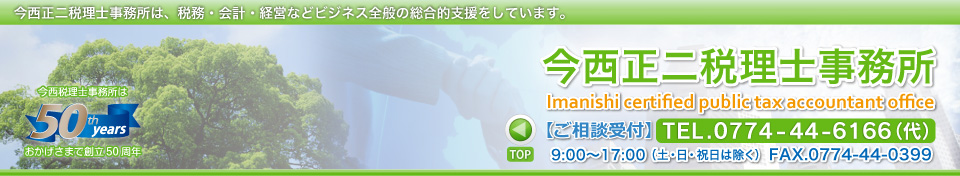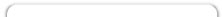 |
 |
 |
 |
|
 |
| →拡大・詳細図をご覧になりたい場合はこの地図をクリックしてください。 |
|
 |
 |
|
 |
 |

 |
 |
| |
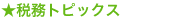 |
| |
|
| |
 |
| 平成28年9月13日 |
| 倒産防止共済制度の概要と掛金 |
 |
倒産防止共済制度とは、独立行政法人中小基盤整備機構が実施する中小企業倒産防止共済制度のことで、次の特徴があります。
① 取引先が倒産して売掛金等の回収が困難になった場合には、支払済掛金の10倍(限度額8,000万円)を限度に、回収困難となった売掛金等の額の範囲内で、無利子で共済金の貸付けを受けることができる。
② 掛金の支払期間が12か月以上の場合は、解約をすると加入期間に応じて支払済掛金の80%~100%の解約手当金が支払われる。
③ 掛金の支払期間が12か月以上の場合には、上記の解約手当金の95%を限度に、一時貸付を受けることができる。
以上の内容から倒産防止共済制度には保険的な性格がありますが、解約すれば掛金が返還され、掛金の累積額の範囲内で貸付を受けることができることから、積立型の保険の要素があります。
税務上の取扱いでは、倒産防止共済掛金の支出は費用ではないので、本来なら個人事業者については必要経費にならず、法人については損金算入できないが、連鎖倒産を回避するための中小企業の共助努力を支援する中小企業倒産防止共済法の要請で、個人所得の必要経費、法人所得の損金の額に対する別段の定めとして、租税特別措置法において特例が設けられたものと考えられます。
このように、倒産防止共済は、本来は費用でないものを、租税特別措置法の特例によって必要経費又は損金の額に算入できる特例ですので、確定申告書に明細書の添付があることを適用要件としています。
法人については別表10(7)「社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」及び「適用額明細書」が該当します。個人事業主については任意の用紙で「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」等を作成し確定申告書に添付する必要があります。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 |
|
| |
|
| |
[一覧へ戻る] |
|
 |
 |
|